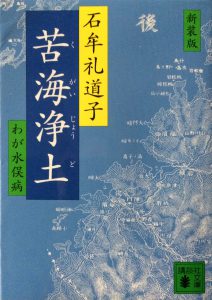
この本「苦海浄土」について何かを書くということは相当の勇気と覚悟が要る。私にその勇気と覚悟があるかと自問すれば一毫もない。しかし「苦海浄土」を読んだことで私が今まで生きてきて稚拙なりにも身に付いた価値観なるものがあったとしたらその価値観に影響を受けたことは否定できない。
水俣の地に住み文学や詩歌に親しむひとりの主婦である石牟礼道子が1965年から一年間発行していた雑誌「熊本風土記」(編集・渡辺京二)に「海と空のあいだに」を連載した。この作品が原型になって1969年に「苦海浄土」が刊行された。
「苦海浄土」はノンフィクションではない、それではフィクションかといえばそうともいえない。著者自身はあとがきで「白状すればこの作品は、誰よりも自分自身に語り聞かせる、『浄瑠璃』のごときもの、である。」とあり、ある談話のなかで「『詩』のつもりで書いた」とあった。書き手の思いからすれば前者の「浄瑠璃」かもしれないが、読み手である私には後者の「詩(ポエム)」という文学形態のほうが相応しいように思った。そしてその「詩」は水俣弁の文体で読み手に迫り私が今まで読んだ詩体とは全く違う新しい文学を切り開いたように思う。
この本を読んで水俣病という社会的不条理を理解したとか被害者の運命に心を寄せて憐憫の情をもったなどという表層的で短絡的な感想を赦さない「何か」が最後のページまで通底している。この本を読むと文体の行間に潜む言葉では言い表せない「何か」が読み手の身体の細胞にじわっと浸潤してくるように思える。社会学者鶴見和子が石牟礼道子の一連の作品について巫女文学であると評したように、石牟礼道子はその「何か」を「詩」という手法で詠い伝える巫女なのではないだろうか。
水俣で手足の硬直や言語障害の症状が幼い姉妹に顕われ、原因不明の病気として保健所に届けた1956年5月1日が水俣病公式確認の日となった。現実には公式確認の日以前にも同じ症状の患者はいたし、61年経った今も水俣病患者として認定されていない患者もいるという。
私たちは様々な技術のお陰で随分と利便的に暮らすことができている。日々の暮らしで便利な物は色々あるが化学肥料やプラスチック製品の種類や物量は圧倒的に多く私たちの生活に浸透している。私はときどき「苦海浄土」が詠い伝える「何か」を忘れて便利な暮らしを安穏と享受している自分に気付く。忘れてはならないのだ、「苦海浄土」は終わりなき問いかけなのだから。