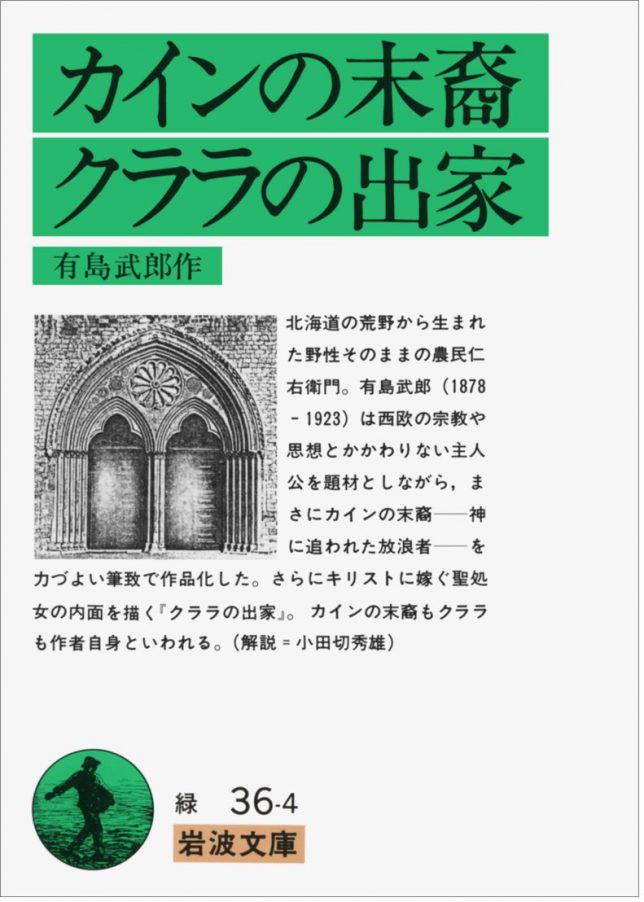
1910年(明43)創刊の同人誌「白樺」から白樺派といわれる文学思潮が武者小路実篤、志賀直哉、有島武郎を中心に起こった。その特徴は人道主義、理想主義といった人間肯定だという。
最近読んだ有島武郎(1878.3.4~1923.6.9)の「カインの末裔・クララの出家」が白樺派の特徴を感じさせるかどうか私にはよくわからないが、有島武郎が一時キリスト教の信仰者だったことが色濃く出ている小説である。
有島武郎がキリスト教に入信したのが23歳、留学して帰国し棄教したのが29歳頃で白樺派が起きたときが32歳だった。そして40歳のときに「カインの末裔・クララの出家」を書いている。
「カインの末裔」の背景は開拓期の厳しい北海道羊蹄山麓で主人公は周囲から疎まれている粗暴な農夫・仁右衛門である。旧約聖書・創世記4章に記されているカインとアベルの物語で神から永遠の罪を背に負うことを課されるカインの化身として仁右衛門が二重写しとして描かれる。読むほどにそもそも罪深きカインの末裔とは今生きる私たちそのものなのだと迫ってくる小説だった。
「クララの出家」は1212年のイタリア・アッシジに家族と暮らす16歳の少女クララが主人公である。クララは聖女となって神に仕える道を志しているが、志と反して異性とのことや家族のことなどへの迷いを夢想する。その無垢で純粋な心の葛藤の末、現世の迷いから決別して聖なる道を歩む決意をする。
この本を読むと棄教してもなおキリスト教の教義の一つである原罪と贖罪という根源的テーマが有島文学の原点だったと思う。そして有島武郎は聖と俗の両極の狭間で死ぬまで悩み続けた人だったと思う。